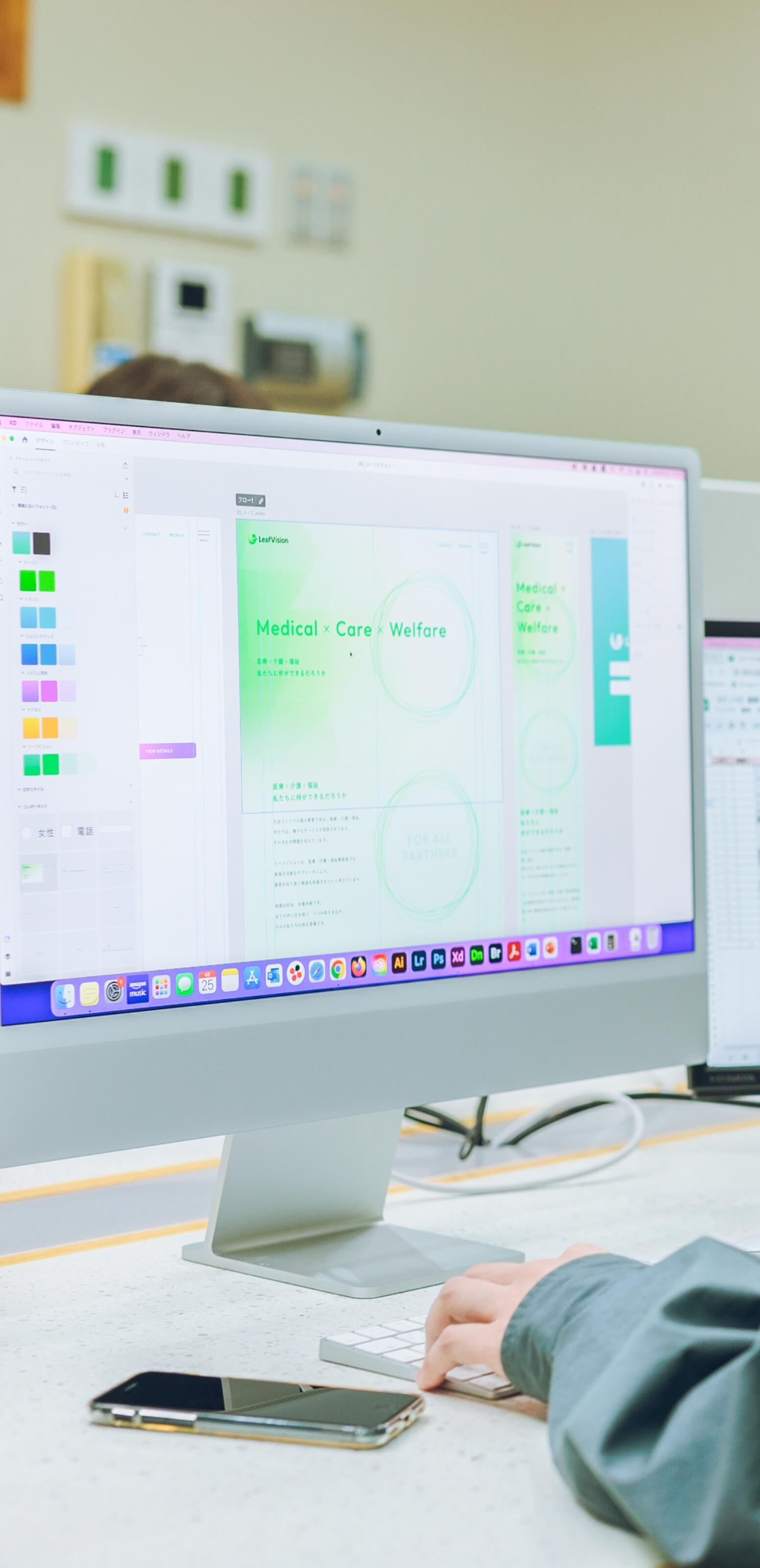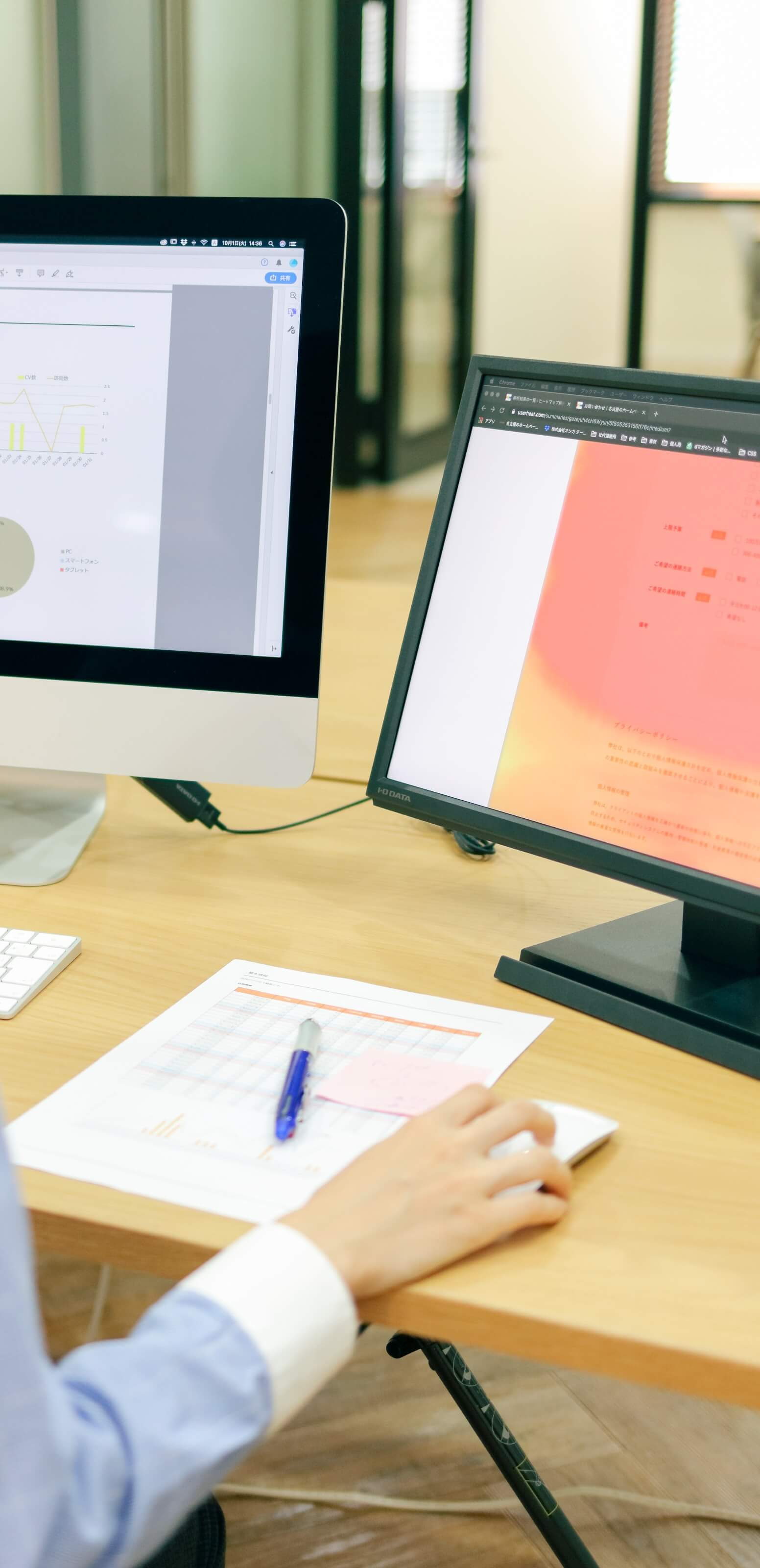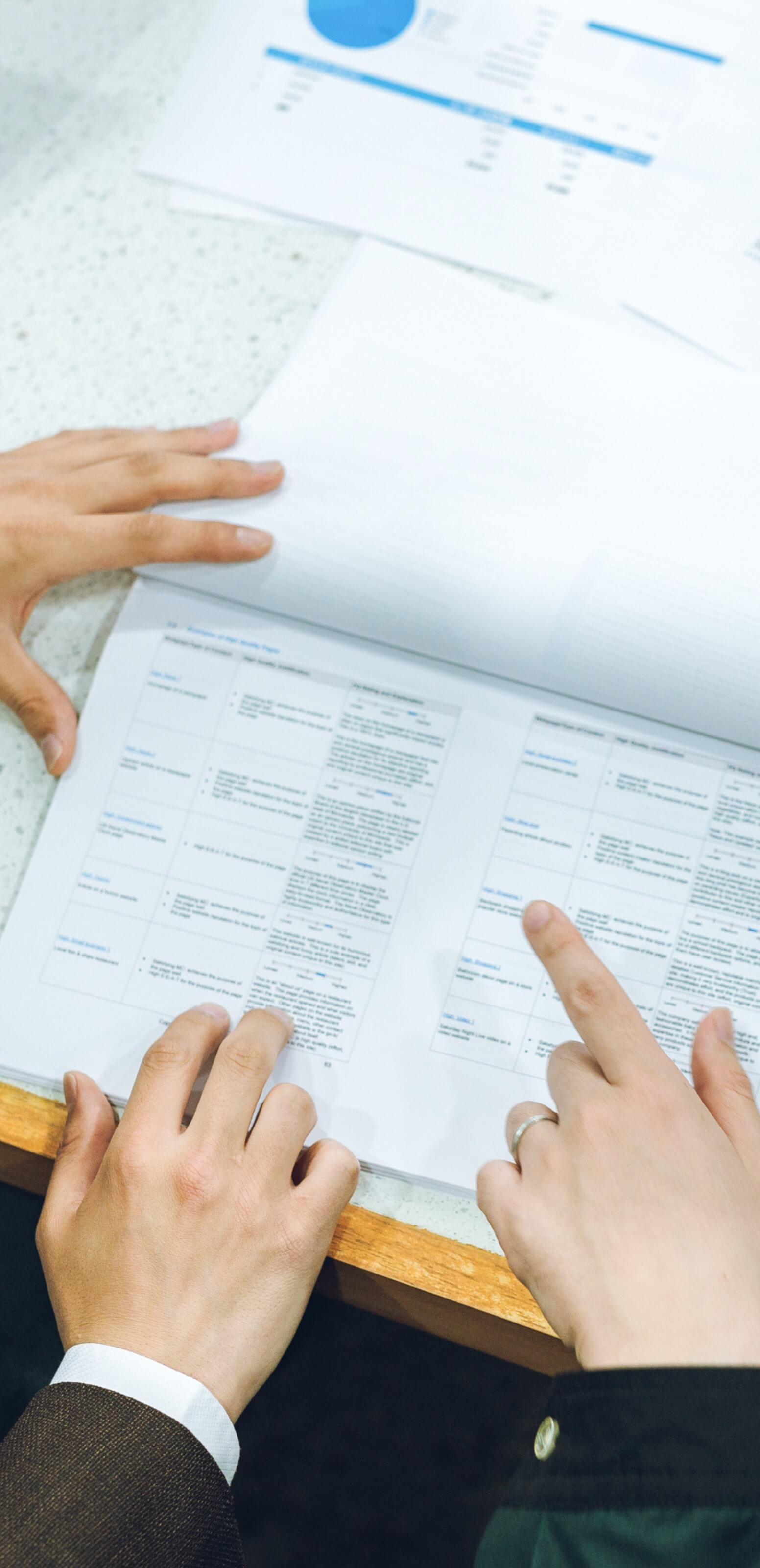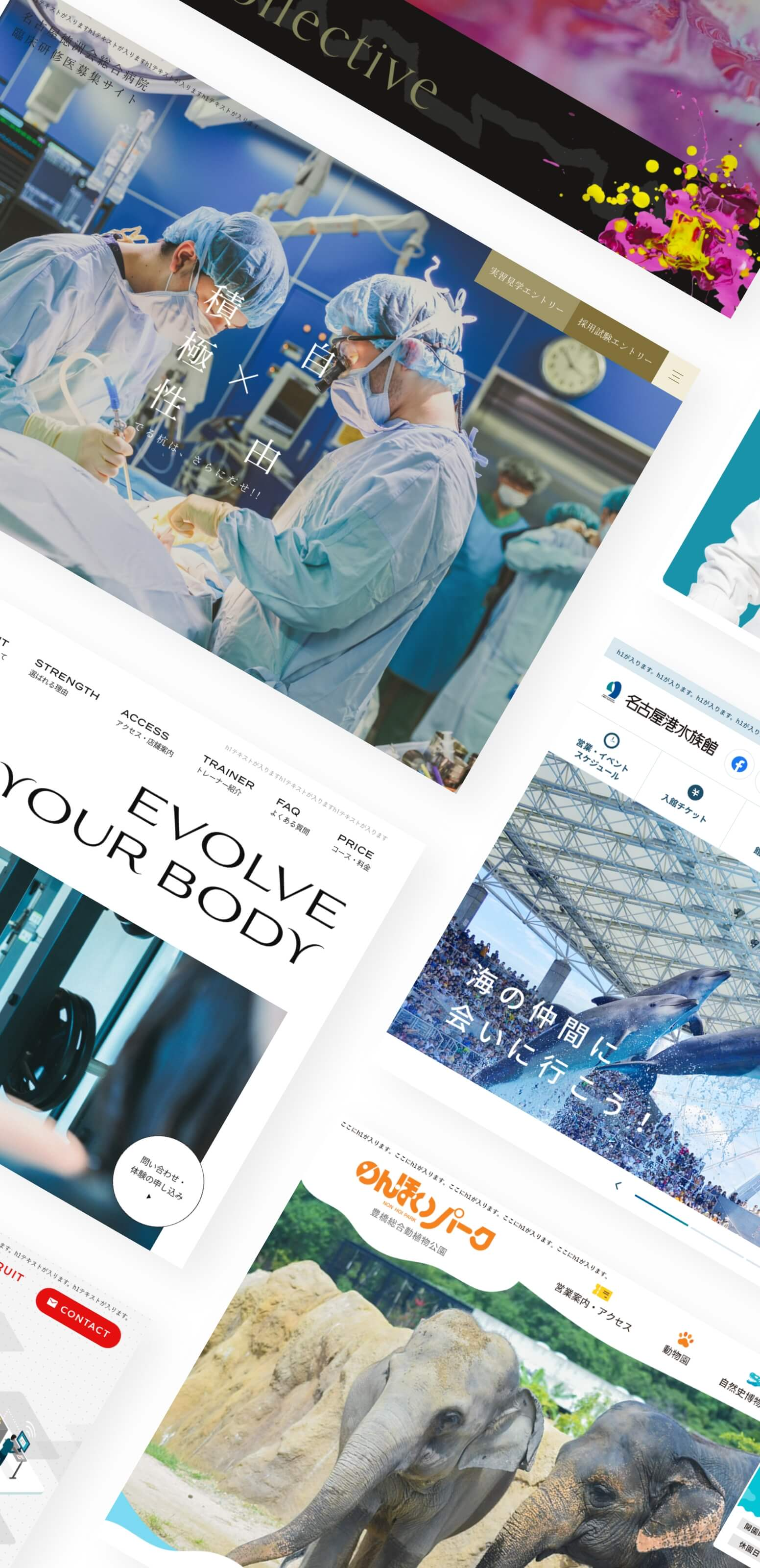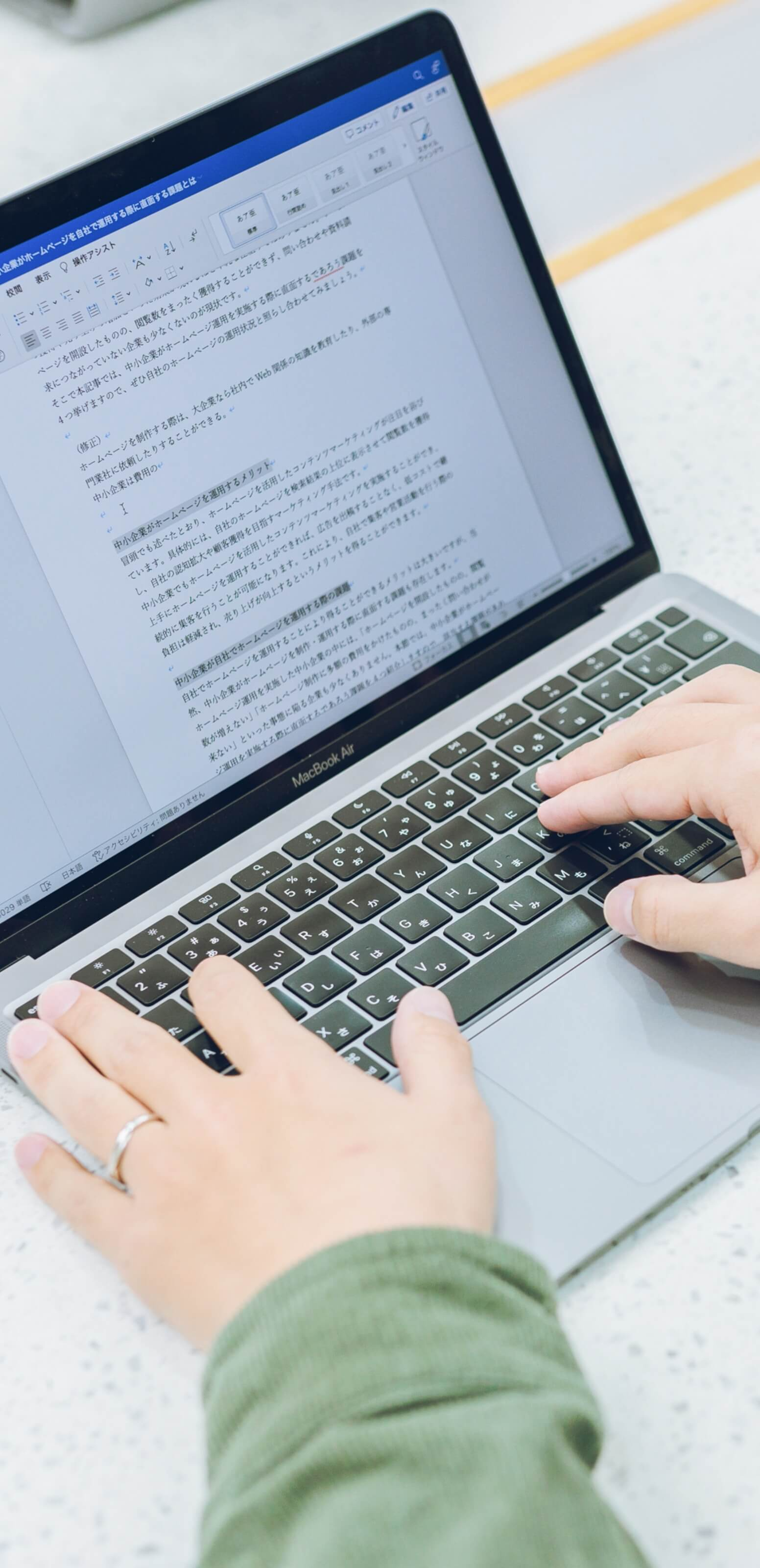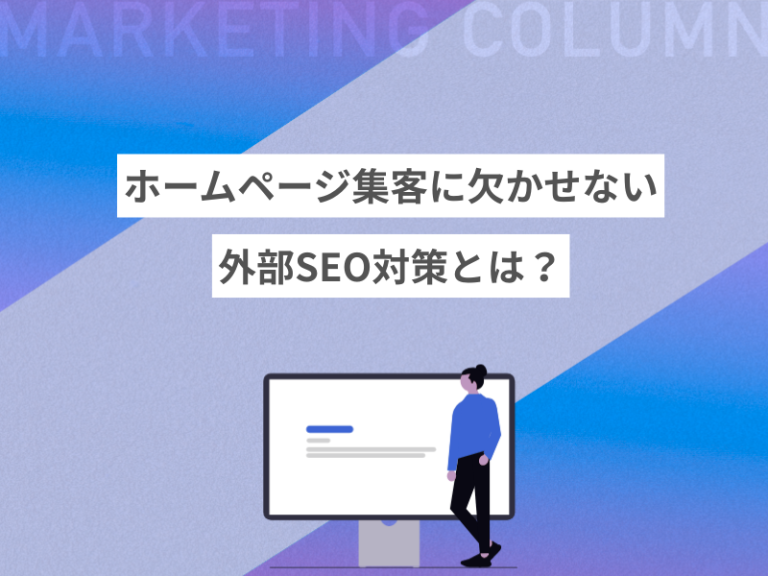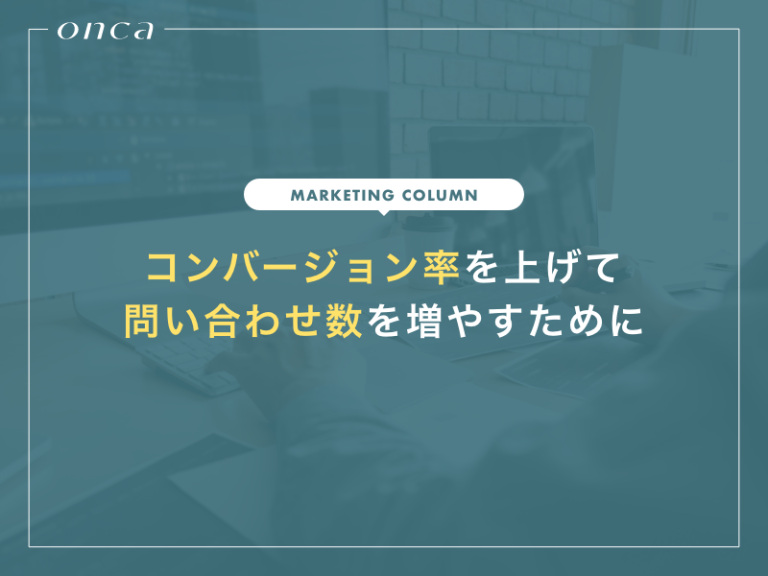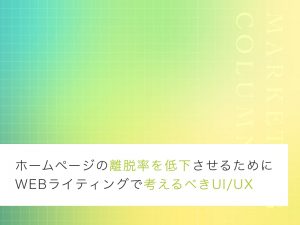NEWS & COLUMN
お知らせ・コラム

SCROLL
MARKETING
2024年上半期におけるGoogleアルゴリズムの大型アップデートまとめ
2024
.07.27
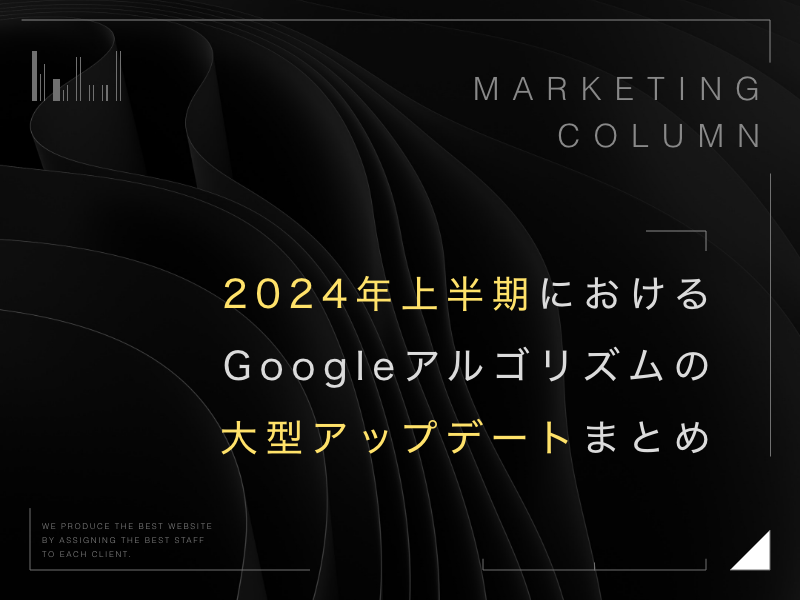
2024年の上半期、Googleは計3回の大規模なアルゴリズムアップデートを実施しました。3回のうち2回は、検索エンジンのガイドラインに違反しているホームページの評価を大幅に下落させる「スパムアップデート」と呼ばれる更新で、ホームページの検索順位が大きく変動しました。
大型のアップデートは、そのどれもがホームページの検索順位に大きな影響を与えるため、ホームページの担当者の方には理解しておいてほしい内容ばかりです。
そこで今回は、Googleが2024年上半期に実施した大型アップデートの内容について詳しく紹介します。
【目次】
3月 コアアルゴリズム・スパムアップデート
2024年の3月5日から4月19日と約1ヶ月半の期間をかけて実施された大型アップデートです。
従来のアルゴリズムアップデートと同様、検索エンジンの品質向上を目的とした変更という点は大きく変化ありませんが、今回のアップデートの最も大きな変更点は、「中古ドメイン・期限切れドメインの悪用」「大量生成されたコンテンツの不正使用」「ホームページの評判の不正使用」のスパムポリシーが新しく3つ追加されたことです。
中古ドメイン・期限切れドメインの悪用
中古ドメイン・期限切れドメインとは、現在は何かしらの理由でその所有権が放棄されているものの、過去にどこかの個人や企業、組織で利用されていたドメインのことです。
ホームページを運用されている方であれば既にご存知かと思いますが、Googleからの評価はホームページそのものではなくドメインに付与されるため、中古ドメイン・期限切れドメインにおいてもGoogleからの評価を引き継いでいます。新規取得したドメインはGoogleからの評価が0からとなるため、中古ドメイン・期限切れドメインを利用することで少なからずスタートダッシュをかけることができます。
当然Googleは、アルゴリズムの抜け道を通って検索結果の上位表示を狙う卑怯な方法を好ましく思っておらず、これまでは注意喚起程度で留まっていました。しかし、今回のアップデートによって、中古ドメイン・期限切れドメインの悪用をスパム行為の対象として明確に指定したため、今後はこのスパム行為の対象として認定されたホームページの検索順位が大きく下落することが予想されます。
○Googleは何を基準にドメイン悪用と認定するのか
Googleは、ドメインの再利用をスパム行為として認定する基準までを公開していません。これは、基準を公開してしまうと、またGoogleの検索エンジンを騙すような手法でホームページを運用する企業や個人が出てきてしまうことを防ぐためです。
ただし、Google検索セントラル内では「検索ランキングを操作する目的で中古ドメイン・期限切れドメインを購入し、ユーザーにとって価値がないコンテンツを提供するために再利用したホームページ」をドメイン悪用したホームページとして評価する旨が記載されています。
また、スパム行為として認定する例も次のように挙げています。
◾️以前に政府機関が使用していたホームページで、アフィリエイトコンテンツを掲載する。
◾️以前に非営利の医療団体が使用していたホームページで、医療関連の商品を販売する。
◾️以前に小学校が使用していたホームページで、カジノ関連のコンテンツを掲載する。
どの例にも共通する項目としては、政府機関や医療団体、教育機関などが利用していた権威あるドメインを営利目的で利用することです。これは営利目的でホームページを運用することそのものに問題があるのではなく、検索エンジンを利用するユーザーを考えてホームページを運用していないことに問題があります。
つまり、「過去に該当ドメインを保有していた企業・組織が少しずつ築き上げてきた評価を悪用し、何の努力もなくお金儲けのために中古ドメイン・期限切れドメインを利用する行為はスパム認定します」と言うことです。
大量生成されたコンテンツの不正使用
大量生成されたコンテンツの不正使用とは、検索ランキングを操作する目的でコンテンツを大量に作成する行為のことです。大量生成関連のコンテンツについては、これまでもGoogleから度重なるアナウンスがありましたが、近年、ChatGPTやBardなどの言語処理技術が搭載されたAIが登場したことで、スパムポリシーとして組み込まれたものと予想されます。
勘違いされがちではありますが、Googleは、このようなAIを利用したコンテンツの作成に否定的ではありません。Google検索チームのアナリスト且つ、SEO関連の情報を提供するスポークスマンでもあるゲイリーイリーズは、2023年に東京で実施されたSearch Central Liveにて、以下のように述べています。
AI生成であることはコンテンツの評価に影響することはなく、最終的にコンテンツの品質が良いものであれば、Googleはコンテンツが作成される過程は気にしません。
ChatGPT を使うこともできますし、Bard を使うこともできます、独自のLLMをトレーニングして使用することもできます。最終結果が高品質である限り、あまり重要ではありません。
このことからも分かる通り、Googleはコンテンツが作成されるプロセスは気にしておらず、結局のところ、検索エンジンを利用するユーザーにとって有益か否かしか見ていません。大量生成することが悪という訳ではなく、むしろAIを利用することでユーザーにとって有益なコンテンツを大量に作成することができるのであればすぐに実践するべきです。
しかし、実のところAIのみの力で有益なコンテンツを作成することは現実問題難しく、どこまで行っても人が介入しないことには有益なコンテンツを作成することはできません。「コンテンツの作成プロセスは気にしない」と言うGoogleの言葉に嘘はないと思いますが、これを間に受けてAIのみでコンテンツを大量に作成し、次の内容に該当してしまうと「大量生成されたコンテンツを不正使用」のスパムに該当することとなります。AIは、アイデア出しや参考程度に利用するツールであり、楽してホームページ検索結果の上位に表示させるツールではありません。
○生成されたコンテンツの不正使用の例
◾️生成 AI ツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すること。
◾️フィード、検索結果、その他のコンテンツをスクレイピングして、ユーザーにとってほとんど価値がない大量のページを生成すること(類義語生成、翻訳、その他の難読化手法などを使用)。
◾️複数のホームページからのコンテンツを、価値を加えることなくつなぎ合わせたり組み合わせたりすること。
◾️コンテンツを大量生成したことを隠す目的で複数のサイトを作成すること。
◾️検索キーワードは含んでいるものの、閲覧者にとってほとんどまたはまったく意味がないコンテンツのページを大量に作成すること。
ホームページの評判の不正使用
ホームページ評判の不正使用は、サブディレクトリ問題やホスト貸し、ドメイン貸しとも呼ばれています。Googleからの評価が高いドメインの配下に自社ホームページを公開・運用することで、上述の2つのスパムポリシーと同様、従来から何度も注意喚起されており、ようやく正式にスパムとして認定されました。
このサブディレクトリ問題については、2023年9月の「September 2023 Helpful Contents Update」、同年10月の「October 2023 Core Update」においてもGoogleが対策していることから考えると、如何にGoogleがサブディレクトリ問題を重く捉えているか想像することができます。
6月 スパムアップデート
2024年の6月20日から6月27日にかけて実施されたスパムアップデートです。
前項のスパムアップデートのような新たなスパムポリシーが追加された訳ではありませんが、クローキングや隠しテキスト、リンクスパムといった従来より存在するスパム行為・ブラックハットSEO対策の検出精度を向上されました。
今回のまとめ
今回のブログを読むことで、2024年の上半期に実施されたGoogleの大型アップデートの概要を理解することができたかと思います。
上半期は、スパム行為・ブラックハットSEO対策を取り締まるためのアップデートが多い印象で、仮に今はスパム行為・ブラックハットSEO対策ではない施策であっても、それが「検索順位の向上」のみを目的としているのであれば、ゆくゆくは取り締まりの対象となり、最終的にその評価を大きく落とすこととなってしまいます。
一時的なアクセス数増加のために上述のような不正な施策を実施することは絶対に避け、Googleのアルゴリズムとウェブマスターガイドラインに準拠してホームページを運営しましょう。