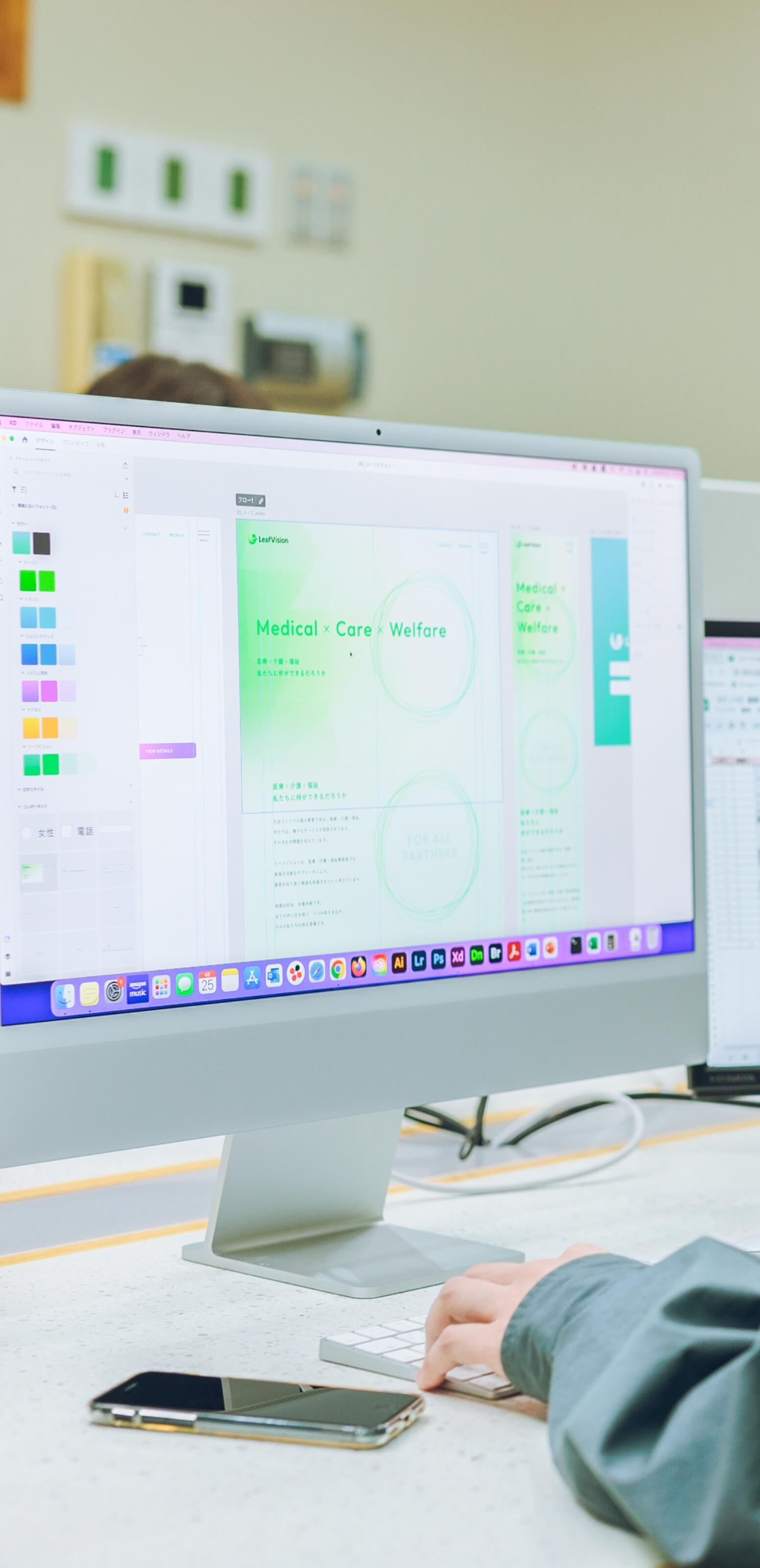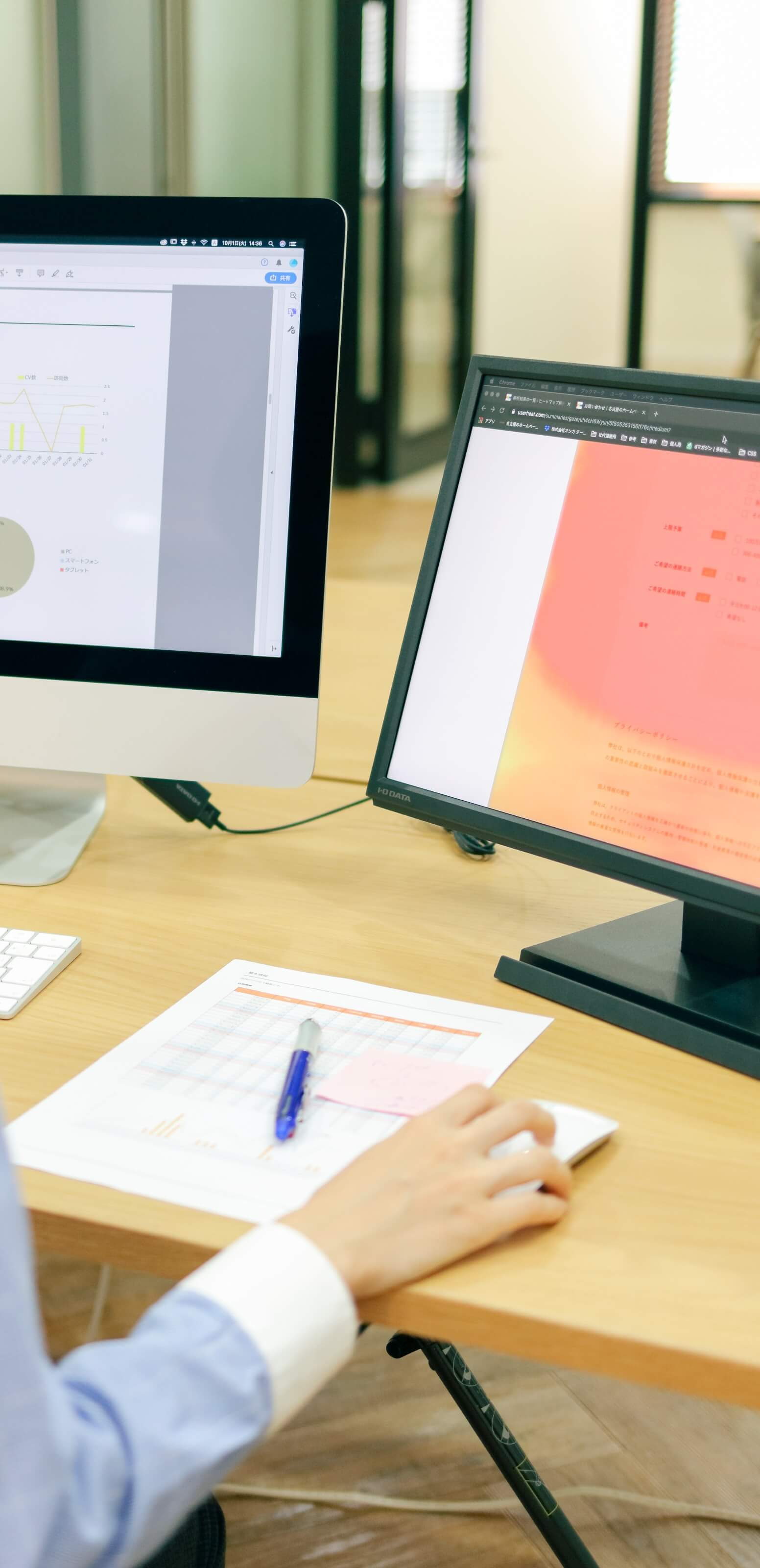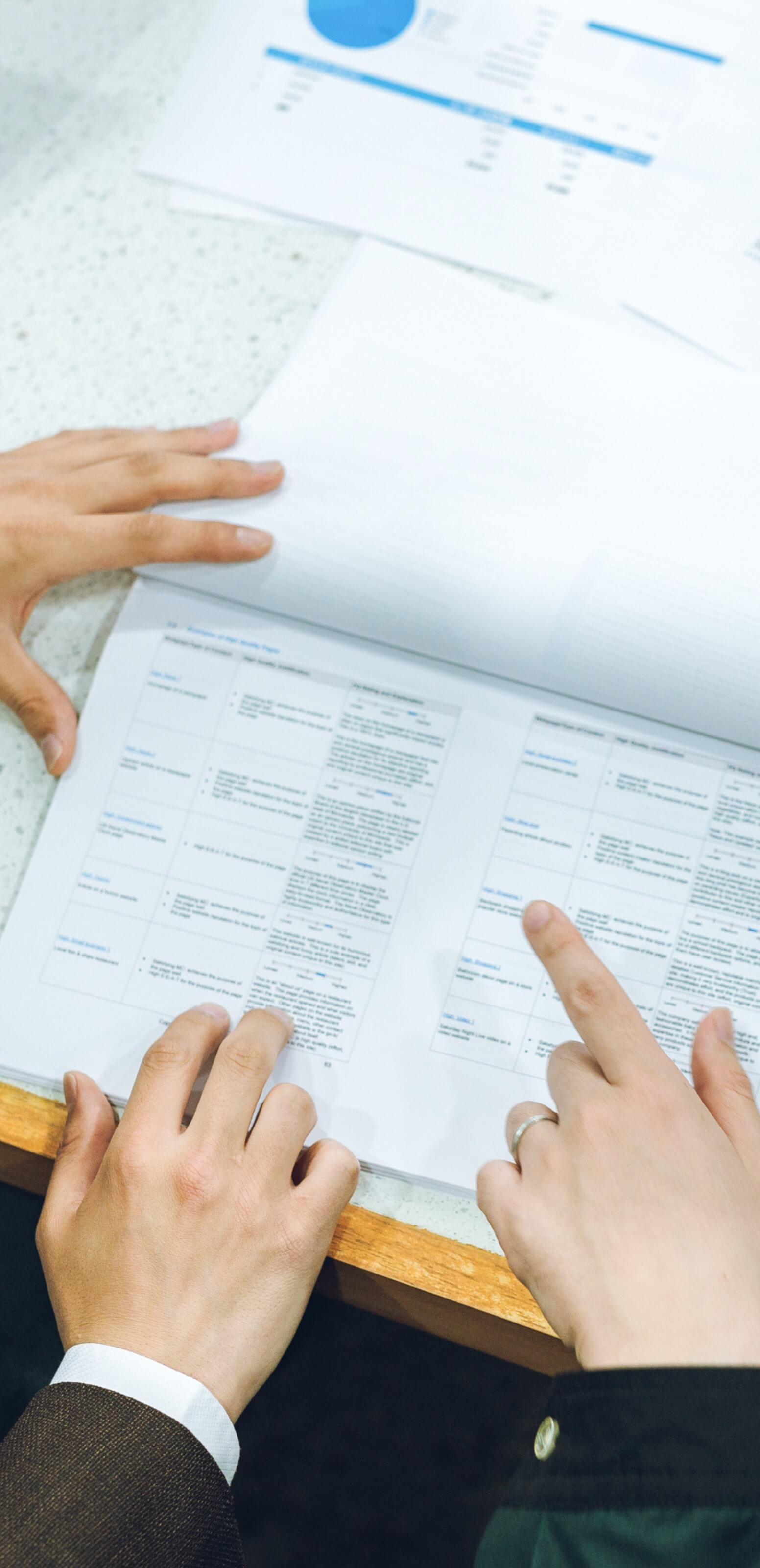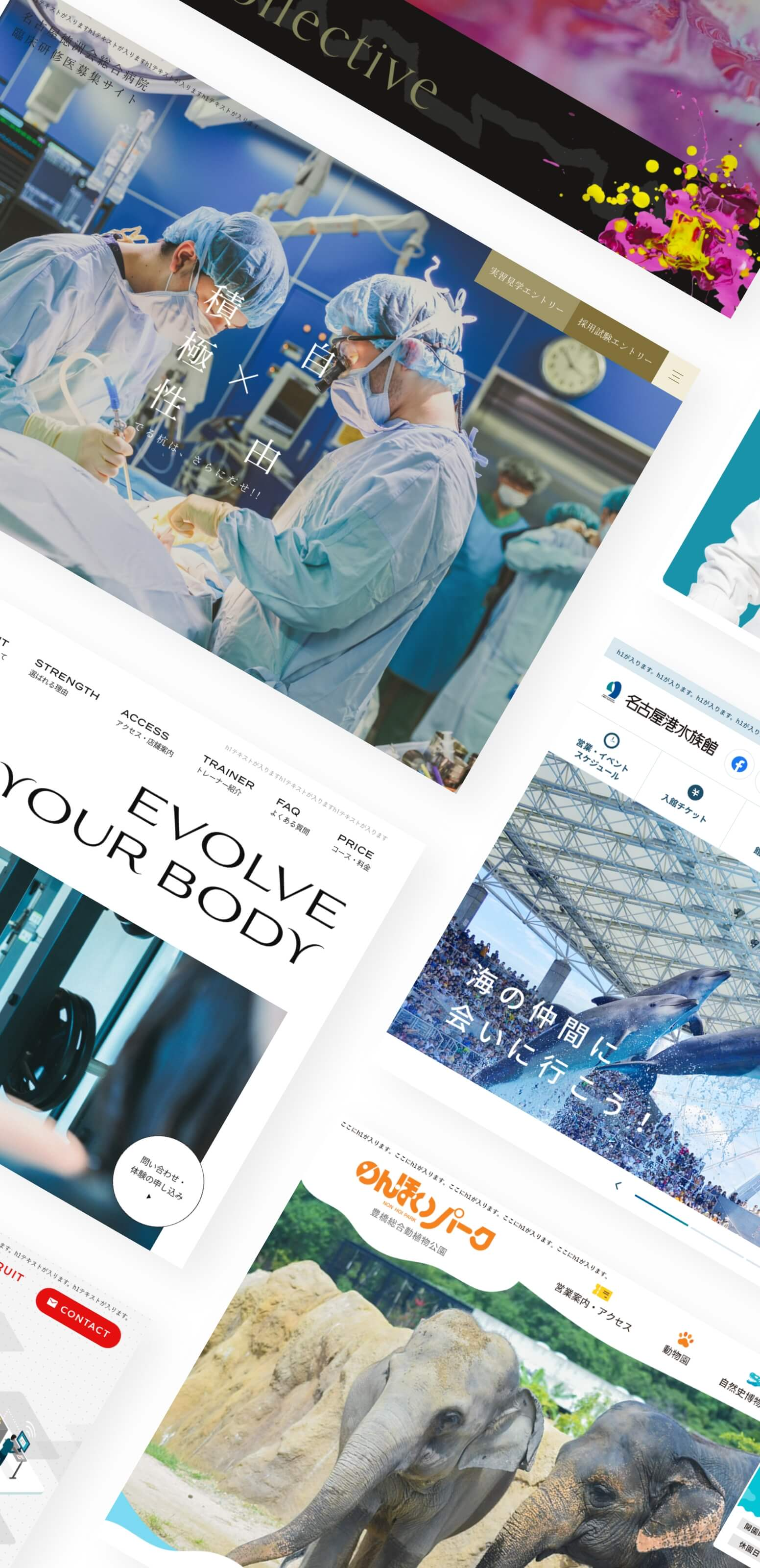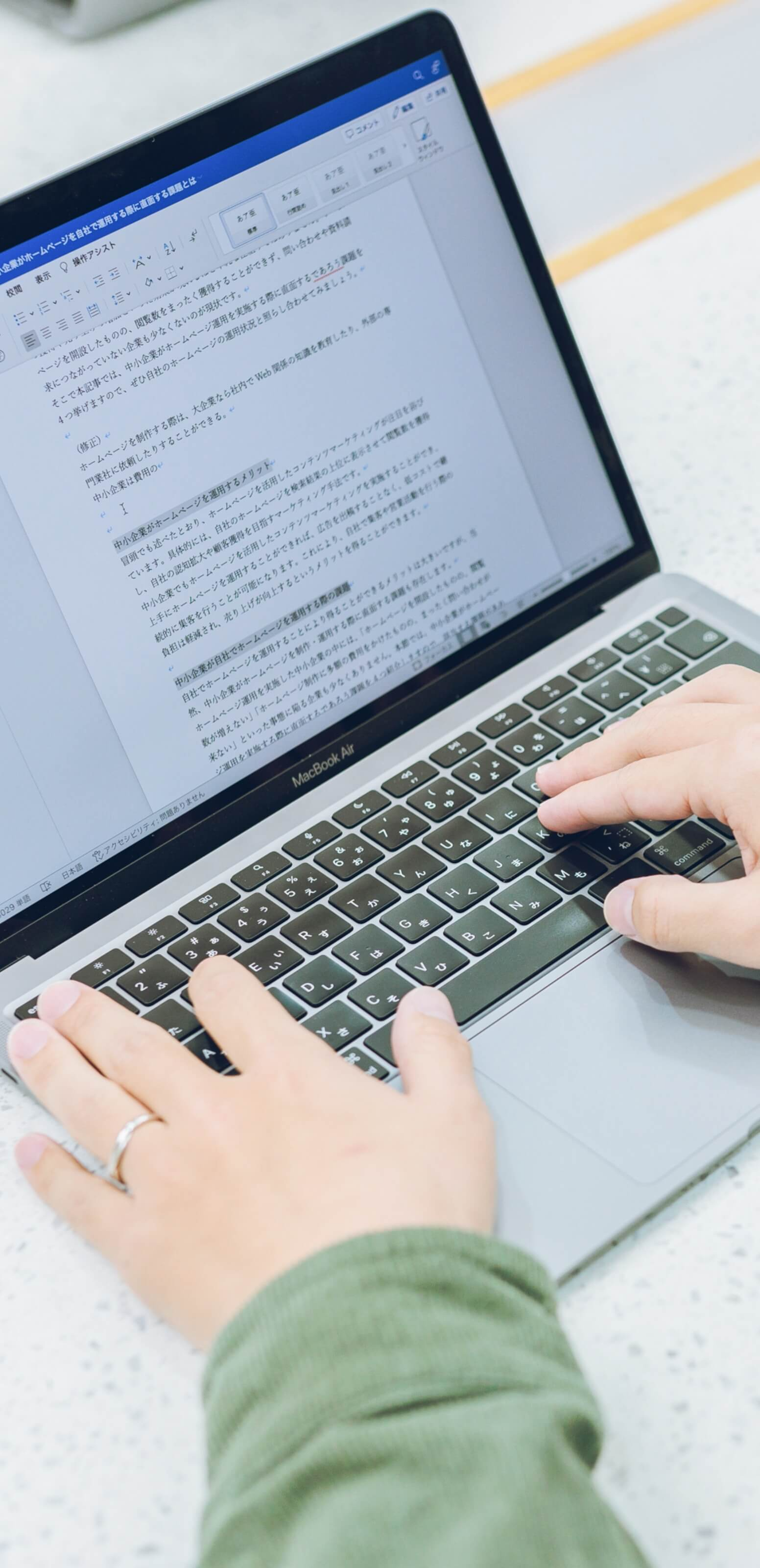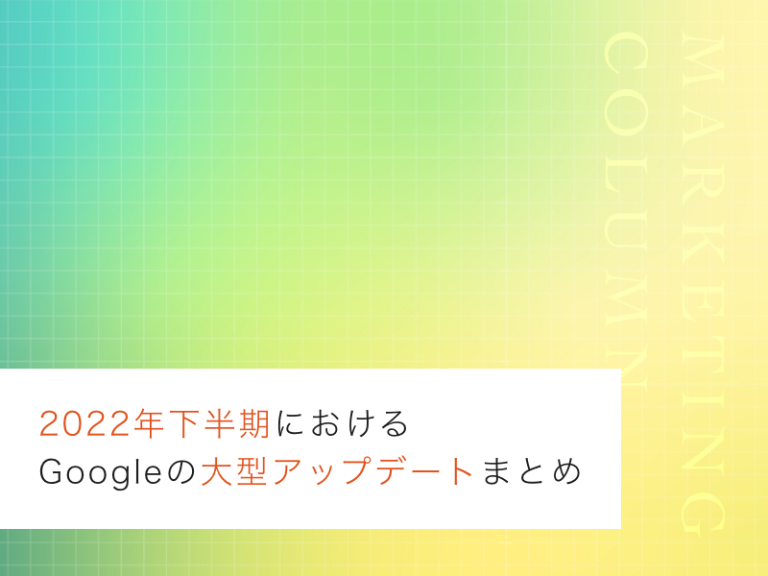NEWS & COLUMN
お知らせ・コラム

SCROLL
MARKETING
ホームページのE-A-Tにおける「信頼性」の考え方
2021
.05.01

Googleがホームページを評価する際の指標としてE-A-Tという考え方を取り入れていることは既にご存知のことと思いますが、この中でも「信頼性(Trustworthiness)」については、どのような対応を行うべきかイメージしにくいのではないでしょうか。
今回は、ホームページのE-A-Tにおける信頼性の考え方とホームページで行うべき対応についてお伝えします。
【目次】
1.ホームページの「信頼性」とは
2.ホームページの信頼性を高めるための8つの方法
a.ホームページ所有者の連絡先を記載
b. ホームページ所有者の所在地やアクセスを記載
c.契約条件等を記載
d.常時SSLに対応
e.プライバシーポリシーを記載
f.購入方法や特商法関連の情報を記載
g.製品の情報や関連するアドバイスを記載
h.外部サイトのコンテンツを引用する場合は著者の情報を記載
3.今回のまとめ
【目次】
ホームページの「信頼性」とは
私たちが誰かから話を聞く際、「その情報は信頼できるものか?」と不安になることがあるかと思います。それと全く同じで、ホームページを閲覧するユーザーも、ホームページに書かれた情報が信頼できるものか否か不安に感じたり、どこか疑いながら見ています。
Googleは、そんなユーザーに少しでも安心して検索エンジンを利用してもらうために、ホームページの評価に「信頼性」という基準を取り入れ、Googleが信頼できると判断したホームページが検索結果の上位に表示されるような仕組みを実装しています。
これにより、「検索結果の上位に表示されるホームページ=Googleが一定の信頼性を認めたホームページ」という図式が成り立ち、ユーザーも安心して情報収集することができるようになりました。
ホームページの信頼性を高めるための8つの方法
上述のとおり、Googleがホームページを評価する際の基準として信頼性という考え方ができましたが、ホームページの信頼性を高めるには、具体的にどのような取り組みを行えば良いのでしょうか。
ここでは、すぐにホームページに実装することができる信頼性を高めるための8つの方法をお伝えします。
ホームページ所有者の連絡先を記載
ホームページの所有者とその連絡先を記載しましょう。どんな情報でも、発信元の素性がわからなければ信用することはできません。誰が発信していて、どこに連絡すれば所有者とコンタクトが取れるのかを明確にして、ホームページに記載する必要があります。
会社のホームページであれば、会社名と代表者名、電話番号、メールアドレスなどを記載することで、所有者をしっかりと明治したことになります。
ホームページ所有者の所在地やアクセスを記載
一つ目と似ていますが、ホームページ所有者の所在地とアクセス方法などを記載しましょう。WEBというものは便利である反面、実態が伴わないため非常に曖昧であるため、ホームページと物理的な場所を紐づけておくことで信頼性が高まります。
例えば、会社の所在地とGoogleマップ、電車や車でのアクセス方法などを記載しておくと良いでしょう。
契約条件等を記載
ホームページを商業利用していてセールスを行う場合は、契約条件やT&Cなどを記載しましょう。
ホームページに書かれた情報がどれだけ素晴らしくても、契約内容が不明確なサービスは歓迎されませんので、必ずホームページ上に明示しておきましょう。
常時SSLに対応
これは当たり前のことですが、常時SSL対応し、ホームページのセキュリティを高めることが大切です。
利用しているサーバーによっては無料かつボタン一つで対応することができますので、サーバー会社に問い合わせてすぐに対応しましょう。
プライバシーポリシーを記載
ホームページで個人情報を取得する可能性がある場合は、個人情報保護法の18条に基づき、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)定めてホームページに記載しましょう。
個人情報の利用範囲や管理方法、保護責任者などの情報を明記し、ユーザーの個人情報がどのように使われているのかをあらかじめアナウンスしておきましょう。
購入方法や特商法関連の情報を記載
商品の購入機能があるホームページ(いわゆるECサイト)では、購入方法や特商法に基づく表記を記載しましょう。
特にBtoCの事業の場合は、特定商品取引法や消費者保護法が適用されるため、しっかりと法令に基づいた記載がなされている必要があります。
製品の情報や関連するアドバイスを記載
ホームページ上で製品を販売している場合は、その製品の具体的な仕様や注意点などを記載しましょう。
例えば、食品のECサイトの場合、商品の賞味期限や原材料、アレルギー物質の表記などを行い、ユーザーが安心して購入できる情報を提供することが大切です。
外部サイトのコンテンツを引用する場合は著者の情報を記載
外部サイトのコンテンツを引用する場合は、引用元の著者の情報を記載しましょう。
ユーザーはあなたのことを信用していても、その先の引用元のことは信用できないかもしれません。そのため、引用元の著者の情報を明記して、ユーザーの安心材料を与えてあげることが大切です。
今回のまとめ
Googleも自社の検索エンジンを安心指定利用してもらえなければ、それだけ利用者数は減り、結果として広告収入が減ってしまいます。そのため、検索結果に表示されるホームページは、極力信頼できるもののみとし、ユーザーに安心して検索してもらえるような環境を整備しています。
今回ご紹介した8つのものは、すぐにでも対応できることばかりですので、まだ対応できていない場合は早急に整備してみてください。